2011年10月23日
2009年10月17日
自作エギ シリコーン型枠製作
 まず手始めにマスターブランクの製作です 市販のパテ、カッター、ヤスリ等を使用し、好みの形に整形していくのですが これから出来上がるエギの原型になりますので気の済むまで手を掛けます マスターブランクにクリヤー塗装などを施すと その後綺麗に型枠が出来るので型枠の寿命も延びると思います |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 油粘土を用意し平らに引き伸ばしますが、この際電子レンジで数秒温めると楽に伸ばせます 次に均した粘土の上にマスターブランクを半分ほど埋め込み、 発泡ウレタンの注入口とエア抜き口も設置します そしてシリコーンの型枠となるプラスチックブロックを設置します 画像ではありませんが、この時型合わせの凸凹も忘れずに施工します |
 発泡ウレタンの型取りの際に使用するシリコーンは 旭化成ワッカー ELASTOSIL M8520 1kgセットを愛用しています メタルジグなど、耐熱性が必要なときは旭化成ワッカー 耐熱ELASTOSIL M4470 1kgセットを使用しています このシリコーンは複雑な形状や複製品を多数必要な場合の型、工業製品・美術品などに広く使われているスグレモノです 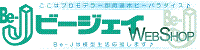 シリコーン等クラフト材料取り扱い店 シリコーン等クラフト材料取り扱い店↑シリコーンのオンラインショップ↑ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 シリコーン(ELASTOSIL M8520)と硬化剤を100:4の割合でよく攪拌します そして綺麗な型枠を作る為、筆などを使い マスターブランクの細かいミゾ、型合わせの凸凹などにシリコーンを入れていきます |
 マスターブランクが隠れるまで流し込み、 硬化するまで半日~一日ほど放置します 硬化したら裏返して油粘土だけを剥がし、 細かいミゾに入った粘土は爪楊枝などで綺麗に取り除きます |
 粘土を綺麗に取り除き、裏面にプラスチックブロックを量増しし、 同じくシリコーンを流し込むのですが この際忘れずに前回流し込んだ面(今回のシリコーンとの接地面)に剥離剤を塗ります 剥離剤を忘れるとシリコーン同士がくっついてしまいます 剥離剤には市販のシリコーンスプレーや、軟膏なども使えるようですが定かではありません そして、硬化すれば型枠の完成です  『シリコーン型作り』へ 『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ 『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ 『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ 『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ 『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ 『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ 『番外編 エギリメイク』へ |
 『シリコーン型作り』へ
『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ
『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ
『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ
『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ
『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ
『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ
『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ
『番外編 エギリメイク』へ 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年09月17日
自作エギ 本体作り
 出来上がったシリコーンに発泡ウレタンを流し込みます 発泡ウレタンはルアー用のライガ製の物を使用します ▼比重が4択できますので好みの物を選択します ルアーキャスト07は約0. 7の比重で重い木のイメージ ルアーキャスト06は約0.6の比重で堅い木のイメージ ルアーキャスト05は約0.5の比重で軟らかい軽い木のイメージ ルアーキャスト04は約0.4の比重で硬質の発泡スチロールのイメージ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 シリコーンの片面にエギのアイの部分(304硬質ステンバネ線を事前に加工しておく) とカンナを付けるグラスソリッド棒をセットし型枠を組み合わせます |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 組み合わせたシリコーン型枠は木の板でボルト止めしてしっかりと固定します |
 ライガ製 ルアーキャスト 0.4硬質発泡スチロール比重を使用しています 次回は0.5比重で試そうと思っています 配合比はルアーキャストA:10、ルアーキャストB:10、 フィーラー:1 電子秤で計測しながらキャストA+フィーラーでよく攪拌し、 キャストBを入れてすばやく攪拌し、数秒以内でシリコーン型に注入します |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 型に流し込んだ発泡ウレタンは数十秒で発泡し始め、 10分ほどで型枠の脱型が可能ですが、0.4比重はガスが抜け切るまで一日放置しています |
 本体が出来上がりましたが、このままでは吸水が激しく Fシンキングのエギになってしまいますので目止めは必須工程です ライガ製のアンダーコートに4回ほどディッピングしていますが それでも吸水してしまう固体がちらほら出てしまい、今後の大きな課題でもあります |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
  この度、知り合いの塗装屋さんに相談し、↑のような塗料(塗料の密着性を高めるシーラー) をいただきましたが、とてもいい感じです アンダーコートと織り交ぜて使っていきたいと思います 最近思いついたのですが 目止めディッピングの際に本体に対してある工程を施す事で確実な目止めが出来そうな方法 を考えましたがその効果は・・・今後アップいたします  『シリコーン型作り』へ 『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ 『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ 『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ 『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ 『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ 『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ 『番外編 エギリメイク』へ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m 『シリコーン型作り』へ
『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ
『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ
『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ
『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ
『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ
『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ
『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ
『番外編 エギリメイク』へ 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年09月16日
自作エギ 下地テープ 布貼り
 本体が出来上がりましたら次は下地テープ貼りです 以前はアルミテープを貼ってエアブラシで塗装していたんですが、 最近はもっぱら100円ショップのメタリック・ホログラムテープを愛用しています その種類の多さとクオリティーで大変重宝しています エギのリメイクにも使えますね |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 主に使っているのが『金テープ』、『銀テープ』、『赤テープ』 時々『紫テープ』や『緑テープ』『ピンクテープ』も使用しますが、メインは前記の3色です 螺旋に巻く方も多いようですが、自分は縦に貼っています 細いテープ(太いものはカッターで半分に)がとても貼り易く、 多少引張って伸ばし気味に貼ると上手く貼れるようです |
  下地テープを貼り終えたら今度は上布貼りですが 下地テープを貼り終えたら今度は上布貼りですが肝心の『布』はエギ布専門店の小上馬で購入しています ←3Mのスプレー糊を上布に吹き付けて貼っています これも引っ張りながら貼っていくと上手く貼れます  ←最近人気の網布もあります |
 張った上布の端を5mmほど残してハサミで切り取り、 カッターの裏などでミゾの中に押し込みます 押し込んだ後は布の剥がれ防止の為セメダインスーパーX などの接着剤を爪楊枝などで溝に沿って塗っていきます |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 エギの前後の布をスレッドで4回ほど巻いて、 ハーフヒッチを3回ほど施して最後は瞬間接着剤で固定します 接着後、前後の余った布をハサミなどで切り取ります  『シリコーン型作り』へ 『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ 『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ 『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ 『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ 『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ 『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ 『番外編 エギリメイク』へ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m 『シリコーン型作り』へ
『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ
『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ
『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ
『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ
『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ
『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ
『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ
『番外編 エギリメイク』へ 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年05月17日
自作エギ 上布塗装
 上布貼りが終わったら次の工程は塗装です エアブラシで蛍光塗料などを吹いていきます 基本的にオレンジが好きですね 一番楽しい時間です  ←Mr.カラー クリアーカラー単品(10ml) |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 リアルタイプの塗装は布貼りの前に多少塗装しておきます |
 仕上げは塗膜保護のためクリヤー塗料に微量のパールを混ぜて軽く吹いています  『シリコーン型作り』へ 『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ 『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ 『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ 『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ 『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ 『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ 『番外編 エギリメイク』へ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m 『シリコーン型作り』へ
『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ
『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ
『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ
『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ
『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ
『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ
『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ
『番外編 エギリメイク』へ 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年04月17日
自作エギ シンカー作り
 自作エギのシンカー作りです まず、鉛を削ったりして調整しながらエギに装着してみて好みの重さ、形に作ります その後、パテ等を盛って仕上げます |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 形が整ったらエギ本体のとき同様、平らに伸ばした油粘土にシンカーの半分を埋め込みます 鉛が流れる口も予め設置しておきます |
 シリコーンの型枠になるプラスチックブロックを シリコーンの型枠になるプラスチックブロックを粘土の上に隙間の無いように設置します  型を合わせる為の凸凹を施します 型を合わせる為の凸凹を施します ELASTOSIL M4470 (耐熱タイプ)を100:2の配合比でよく攪拌し、筆などで細かいところにシリコーンを塗ってから流し込みます ELASTOSIL M4470 (耐熱タイプ)を100:2の配合比でよく攪拌し、筆などで細かいところにシリコーンを塗ってから流し込みます ←■ELASTOSIL M4470 1kgセット(耐熱タイプ) 低粘度で作業性が良く、高硬度で耐熱性が必要なシリコーンゴム型を作ることが出来ます。 |
 片面にシリコーンを流したら半日~一日ほど硬化を待ちます 片面にシリコーンを流したら半日~一日ほど硬化を待ちます 硬化を確認したら油粘土を剥がし、 硬化を確認したら油粘土を剥がし、細部に残った粘土を爪楊枝などを使い取り除きます そしてシリコーン同士がくっついてしまわないように 剥離剤(軟膏など)を筆などでシリコーン面に塗ります  剥離剤を塗り終えたらプラスチックブロックで型枠の量増しをします 剥離剤を塗り終えたらプラスチックブロックで型枠の量増しをします 残りの片面にシリコーンを流し込み、再度硬化するまで放置します 残りの片面にシリコーンを流し込み、再度硬化するまで放置します |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
 残りの片面も硬化が確認できたらプラスチックブロックの型枠を脱型します 残りの片面も硬化が確認できたらプラスチックブロックの型枠を脱型します ばらしてシンカーのマスターブランクを取り出します ばらしてシンカーのマスターブランクを取り出します 鉛の流入口を彫刻刀で削ります 鉛の流入口を彫刻刀で削ります 鉛がよく流れて表面が綺麗になるように 鉛がよく流れて表面が綺麗になるようにパールマイカ(ファンデーションでも代用できるそうです)を筆で シンカーの表面部分に塗ります |
 エギ本体のとき同様、木板でシリコーン型を挟み込みボルトで固定します |
 ガスコンロで鉛を熱して溶かします ガスコンロで鉛を熱して溶かしますこの時、鉛の硬度を出す為『アンチモン』・『錫(スズ)』を鉛の10%ほど 溶かします くれぐれも鉛中毒にならないように換気は十二分に行ってください  鉛を流し込む際は 鉛を流し込む際はとても高熱になっていますので火傷に注意が必要です  鉛が十分冷めるのを確認してシンカーを取り出します 鉛が十分冷めるのを確認してシンカーを取り出しますこの際も火傷に注意です 必ずペンチなどで取り扱いましょう  ←硬質鉛素材 ハードウェイト 1,000g ←硬質鉛素材 ハードウェイト 1,000g ジグ製作用硬質鉛(錫・アンチモン配合) |
 十二分に冷まして、バリを取ったら完成です  『シリコーン型作り』へ 『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ 『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ 『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ 『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ 『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ 『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ 『番外編 エギリメイク』へ |
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m 『シリコーン型作り』へ
『シリコーン型作り』へ 『エギ本体作り』へ
『エギ本体作り』へ 『下地テープ 布貼り』へ
『下地テープ 布貼り』へ 『上布塗装』へ
『上布塗装』へ 『シンカー作り』へ
『シンカー作り』へ 『カンナ作り』へ
『カンナ作り』へ 『仕上げ』へ
『仕上げ』へ 『番外編 エギリメイク』へ
『番外編 エギリメイク』へ 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年02月28日
カンナ作り
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
2009年01月26日
仕上げ
 皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m
皆さんの技…勉強になりますm(_ _)m








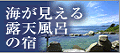
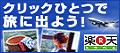





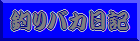
 釣りバカ日記>
釣りバカ日記>
 自作エギ製作
自作エギ製作






 コンプレッサー&エアブラシセット
コンプレッサー&エアブラシセット スプレーブース
スプレーブース 軽量高速型ルーター
軽量高速型ルーター ダストキャッチャー【PROXXON(プロクソン)】
ダストキャッチャー【PROXXON(プロクソン)】 シミズ☆ヤエン工房(手作りキット・ハンダ用)
シミズ☆ヤエン工房(手作りキット・ハンダ用) アルミ粘着シートダイヤモンドモールド(75mm×255mm)
アルミ粘着シートダイヤモンドモールド(75mm×255mm) 【Woody Rebass(ウッディーリバース)】
【Woody Rebass(ウッディーリバース)】 セルロースセメント・クリヤー(500ml)
セルロースセメント・クリヤー(500ml) ウレタンコートLRプラス/URETHAN LR+(350ml)
ウレタンコートLRプラス/URETHAN LR+(350ml) セルロースセメントUVスプレー(クリアー/300ml)
セルロースセメントUVスプレー(クリアー/300ml) SGIクレオス Mr.カラー(スーパーメタリック)
SGIクレオス Mr.カラー(スーパーメタリック) Mr.カラー マジョーラ[コスモコレクション]18ml各色
Mr.カラー マジョーラ[コスモコレクション]18ml各色 グローライブアイ(GLOW LIVE EYE)夜光/黒瞳
グローライブアイ(GLOW LIVE EYE)夜光/黒瞳  エポキシハンドレッドコート
エポキシ樹脂塗料
エポキシハンドレッドコート
エポキシ樹脂塗料 ステンレスワイヤー #18(1.1mm~1.2mm) 6m
ステンレス製汎用ソフトタイプ
ステンレスワイヤー #18(1.1mm~1.2mm) 6m
ステンレス製汎用ソフトタイプ 304ステンバネ線各サイズ長さ500mm [線径:0.8mm/1.0mm/1.2mm]
304ステンバネ線各サイズ長さ500mm [線径:0.8mm/1.0mm/1.2mm]


